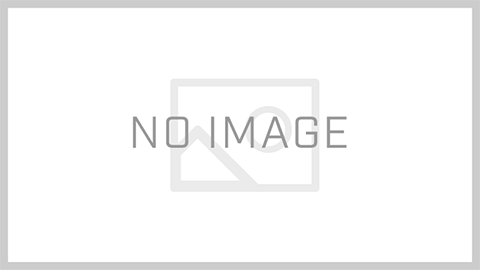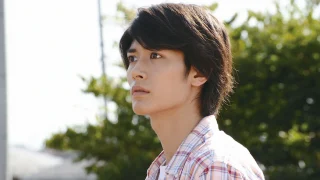(C)2013「永遠の0」製作委員会
太平洋戦争末期。勝利目前のアメリカを大混乱に陥れた、一機の戦闘機。「悪魔」と呼ばれたゼロ戦は、米軍最強の空母艦隊による一斉射撃・百万の銃弾をくぐり抜け、包囲網を突破したのだ。その「悪魔」を操るパイロットは、宮部久蔵。天才的な操縦技術を持ちながら、生還することにのみ執着し、「臆病者」と蔑まれた男だった…。
そして時は2004年、現代。進路に迷う佐伯健太郎は、祖母・松乃の葬儀の日に驚くべき事実を知らされる。本当の祖父の名は、宮部久蔵。太平洋戦争で零戦パイロットとして戦い、終戦直前に特攻出撃により帰らぬ人となっていた。「家族のもとへ、必ず還ってくる」…それは宮部が妻・松乃と娘・清子に誓った、たったひとつの約束だった。そんな男がなぜ特攻を選んだのか。宮部が命がけで遺したメッセージとは何か。そして現代に生きる健太郎は、その思いを受け取ることができるのか。
(C)2013「永遠の0」製作委員会
作品情報
| 監督 | 山崎貴 |
|---|---|
| 出演 | 岡田准一/三浦春馬/井上真央 |
| 主題歌 | サザンオールスターズ 「蛍」 |
| ジャンル | 戦争・アクション |
| 時間 | 2時間23分 |
| 制作 | 2014年 東宝 |
| おススメ度 |
Amazonプライムで見放題です。
※ネタバレ含む内容となっているため、まだ視聴されていない方はご留意ください。
感想(ネタバレ含)
司法浪人中の佐伯健太郎(三浦春馬)は、祖母・松乃(井上真央)の葬儀の日に母・清子と姉・慶子から祖父・大石賢一郎と再婚していたことを聞き、本当の祖父の存在を知ります。本当の祖父・宮部久蔵は、零戦パイロットとして太平洋戦争に従事し、終戦直前に特攻出撃によって戦死していました。
フリーライターの慶子は、宮部久蔵の過去を調べて本を出版しようと思い、健太郎に調査の協力を頼みます。健太郎は賢一郎の許可をもらい、2人は生前の宮部久蔵を知る人物に取材をはじめます。しかし、海軍航空隊時代の同僚たちは宮部久蔵のことを“海軍一の臆病者”と非難します。健太郎は会う人すべてに宮部久蔵を臆病者と言われたことから、モチベーションが下がっていきます。そんなときに訪ねた景浦に「祖父は臆病者だったんですよね」と言ったことで、景浦を激怒させてしまい追い出されてしまいます。健太郎と慶子はは本当の宮部久蔵はどのような人なのかと困惑します。
つぎに訪ねた海軍航空時代に宮部久蔵の部下だった井崎は、宮部久蔵についてくわしく話を聞かせてくれます。井崎は宮部久蔵がどれだけ腕のよいパイロットであったのか零戦についても詳しく説明する。
昭和16年の真珠湾攻撃での成功に、宮部久蔵や井崎の所属する海軍航空隊は沸き立ります。しかし宮部久蔵だけはアメリカ軍の空母を潰せなかったことで先の戦局を心配し、死んでいった仲間を思い沈んでいました。翌年、宮部久蔵の懸念通りミッドウェー海戦で、日本軍の空母は撃沈され海軍航空隊は母艦を失いました。
昭和17年に宮部久蔵たちはラバウルへ送られ、そこで井崎は宮部久蔵直属の部下となります。井崎は宮部久蔵がなぜ生きて帰ることに固執するのかわかりませんでした。宮部久蔵は自分一人ならそれでもいいが、自分が死ぬと妻と娘の人生を狂わせてしまうのでなんとしても生きて帰るのだと語ります。しかし戦況はますます激しくなり厳しい状況へ追い込まれていきます。
そんな中、宮部久蔵率いる部隊の1人が燃料が無くなり離脱、海の上に不時着したが海には沢山のサメがいる場所であった。宮部久蔵は部下が特攻するのを良しとしませんでした。敵機に突っ込めば間違いなく死んでしまいますが、海の上なら万が一でも生き延びる可能性があるといいます。井崎は「どうせ死ぬなら敵へ突っ込んで自爆した方がいい」と言いよしますが、宮部久蔵は「どんな時も最後まで生き延びる努力をしろ」と怒ります。その言葉は井崎の胸に深く突き刺さり、自身がマリアナ沖海戦で海に落ちたとき、何度もダメだと思いながらもグアムまで泳ぎ続ける励みとなりました。
「生きたい」「死にたくない」と言えないあの時代で、言い続けた宮部久蔵は誰よりも強い人だったのだと井崎は話しました。そして宮部久蔵が前線へ送られる前に一度だけ、横浜に戻り松乃と清子に会っていたという事実を健太郎と慶子は知ります。そして宮部久蔵は、「家族のもとへ、必ず還ってくる」と松乃と清子に約束していたと。
井崎の話を聞き、健太郎はもっと宮部久蔵のことを知りたいと思い始めます。なぜ臆病者と言われながらも生きて帰ることにこだわっていた宮部久蔵が、なぜ特攻に志願したのか。
大企業の会長である武田は、昭和20年に学徒出陣で徴兵され、海軍航空隊予備学校の教官の宮部久蔵の訓練を受けていました。学徒生には特攻志願書が配布され、ほとんど全員が特攻を志願しましたが、飛行訓練で宮部久蔵は生徒に「可」をだしませんでした。なかなか戦場へ出してもらえない生徒たちはそんな宮部に不満を持っていました。あるとき宮部久蔵は訓練中に亡くなった生徒を侮辱した上官に反論して暴行を受けます。生徒たちは仲間の名誉を守ってくれた宮部久蔵に感謝し尊敬するようになります。
武田の話を聞き健太郎は改めて景浦を訪ねると、景浦は健太郎の変化を知り宮部久蔵の話を聞かせてくれました。景浦は宮部久蔵と同じ海軍航空隊に所属していました。戦闘を好む景浦は、宮部に強い反感を持っていました。しかし自分の浅はかで愚かな挑発を見事にかわした宮部久蔵の腕前を認めざるを得ませんでした。
その後、昭和20年に景浦は鹿屋基地で宮部久蔵と再会します。生きることにこだわり続けた宮部久蔵の姿はそこにはありませんでした。特攻出撃で敵陣にたどり着けないまま命を落としていく生徒たちを見続け、宮部久蔵は自分の無力さに打ちのめされていました。そしてついに宮部久蔵は自ら特攻を志願しました。
強い意志を持つヒーロー
永遠の0は、複数のエピソードで構成されており、それぞれのストーリーから主人公・宮部久蔵の心の変化を、どういう時代だったのかを追体験するような形で進んでいきます。
主人公の宮部久蔵は「生きて妻子の元に戻る」という強い意志を持ち、そのために「臆病者」と呼ばれ罵られても暴行されても考えを曲げることはありません。そこに物語のヒーローたるものを感じます。生きることに執着し、このままどんな困難があってもきっと最後は妻子の元に戻るんだろうな……という未来を感じさせるようなストーリーが序盤にあります。
原作にはない戦時中にたった一度、横浜へ帰省した時のストーリーでは、子どもへの愛情や妻子のために必ず戻ってくるという強い意志を感じます。
にも拘わらず、宮部久蔵は特攻隊員として戦死します。そこがこの物語のポイントになる部分なのだと思います。敵艦にたどり着かずに終わってしまうことが多いのに、たくさんの学徒動員を見送り、最後は自分がそこへいきます。自分が乗る予定だった零銭の不調が分かっていて交換したのです。
そこにどんな思いがあったのか?
推測しては消え、推測しては消え、きっと複雑にさまざまな背景や感情や現実が絡み合っていて、『答え』にはたどりつきません。これが物語の中にある1つの現実につながる部分なのかなと思います。
私たちの多くは戦争を知りません。どのような時代であったのかも聞いた話、残された資料からでしか読み取れません。そこに答えはあるのでしょうか。答えは数えきれないくらい沢山あるのでしょう。
私は、私だったら、最後まで自分から希望はしません。でも、宮部と同じようにたくさんの学生を見送っていたとしたら、私も心はボロボロになっていたかもしれません。だとすると、宮部のようにすべてを終わらせるべく零戦に乗った人も、家族のために乗った人も、戦地へ学徒出陣させることが正しいことだと思う(思い込む)人も、国のために死ぬ(死ね)という人も、みんなそれは正解なのかもしれないという気もします。
自分の心を守るためには、自分の大切なものを守るためには、何かにすがらなければならないこともあるのではないでしょうか。それが、死ぬことなら、戦地へ送り出さなければならないことなら、大変つらいもので今のこの世であってはならないことだと思います。
どうして武力を出さなければならないのか。
なんで過去の過ちを繰り返えさなければならないのか。
いまのこの世界情勢をみて私は『戦争』に正義はないと思うし、多くの人が望んでいないはずなのにどうしてこのようなことになるのかととても苦しく思う。
昔は宮部が許せなかった
おそらく最初にこの映画を見たのは公開したころなので、私が社会人になったころだと思います。その頃は映画を見て戦争の理不尽さを感じつつも、主人公・宮部が許せませんでした。松乃に約束をしたのに自分から特攻へ志願し飛んで行ったから。松乃の視点で物語を見て、自分が松乃の立場だったらと考えるとどうしても納得できませんでした。どんなことがあっても帰るべきだと思ったのです。あんなに罵られても、暴力を受けても、生きるための行動しかしてこなかったのに。
そして、同時に松乃にたいして薄情さも感じていました。宮部の帰りをあんなに待っていても、最後は絆されて違う男性を好きになるのかと。たとえ宮部への思いは消えていないのだとしても、再婚するのかと。
あれから10年ちかくたち、いまこの映画をみると宮部の気持ちもわからなくないのです。生きたい気持ちと帰りたい気持ちは変わっていないのだろうと推測します。でも、失われていく命、死に向かう学生たちを見送りつづけて、心が”普通”ではなくなってしまった、壊れてしまったんだとも思うのです。
この戦争をこれで終わらせたい
そんな気持ちもあったのではないかなと。
そして、松乃の気持ちの変化にも物語の中で話されているように宮部のことを忘れたことはなかったというのも、言葉にすることは難しいのですがその意味がわかるようになった気がします。
さまざまな気持ちと折り合いをつけながら、悲しみや怒りやそういった感情を慰めながら、少しずつ前を向いて生きているのだと思います。
物語だからこそ
映画を見てからこの感情を誰かと共有したいと思い、口コミをいろいろ読みました。その中で「そういう時代ではない」「生きたい・死にたくないというのはおかしい」というおいっと突っ込みたくなるようなものも見かけました。
この物語はそういう時代だったからこそ、みんなが隠していた思いを、主人公が「生きる」ことに執着すことで代弁し、そしてどんなに強い心を思いを持っていても折れてしまうところに、折れてもなお消えてはいない「生きる」ことへの思いが、自分ではどうにもならない理不尽さが、その時代が浮き彫りになっていると思います。
そこが物語の中にある「真実」なのではないのでしょうか。
何度も映画化を断っていた
著者の百田さんがどのような思いで執筆されたのかと調べていたところ、「JFN Online ラジオ版 学問ノススメ」という番組でお話されているのを見つけました。
百田尚樹さんはもともと放送作家であることもあり、映像も意識してはいたとのこと。しかし、何度も映画化の打診があったもののシナリオに納得ができず何度も映画化ドラマ化を断っていたそうです。というのは原作小説はとてもボリュームがある作品なので、映画の2時間30分に収めようとするとどうしてもたくさんあるエピソードを削らなければならないことがあり、ご自身でも脚本を検討されたこともあったそうですがとても難しかったそうです。
小説を読まれた方、映画を視聴された方はご存じでしょうが、永遠の0はたくさんのエピソードから成り立っていて、どれもかれも欠かせないストーリーで。百田さんがおっしゃられている意味が分かる。そこから映画にまとめるって、監督の山崎貴さんってすごい方ですよね。百田さんも山崎監督のシナリオを見てこれならと映画化することになったそうです。
オープニングから引き込まれる映像が沢山あり、特に零戦は現存するエンジンの音を録音されたそうで、臨場感あふれる映像になっています。また、真珠湾攻撃の後に家族の元へ帰ったシーンでは、原作ではどのような会話をしたのかは触れられておらず、読者の想像にまかせていますが、映画ではこのシーンが追加されています。ここで宮部が松乃に言った「必ず生きて帰る」というセリフは私も最後まで最後までずっと消えずに残っていました。この映画で一番心に残る重要なキーワードになっています。
百田さんは『大東亜戦争はどういう戦いだったのか、その背景、その舞台時代の中でどのような思いをもって生きたかを描きたかったかった。生きるということのすばらしさ、今どれほど恵まれた世界で生きているのかということをつたえたかった。』と話されていました。
永遠の0で子供の世代と父の世代をつなぎ合わせたかった。という。
その通りで、私は健太郎の視点で過去にさかのぼって考える時間をもらったように思います。
私の曽祖父と高祖母に思いをはせる
私の祖父母は昭和初期の生まれでしたので太平洋戦争中は10代半ばごろでした。しかし祖父は幼いころに亡くなっていており、祖母からは戦時中は大変だったということを少し聞いたことがあるだけで、戦時中の話を聞いたことはありません。曾祖母も戦争について話したことはなかったように思います。祖母も曾祖母も実体験を私に話したことはあまりありませんでした。しかし祖父や祖母は母には話していたようで、その話をよく母から聞かされました。
授業ではなく敵兵を竹やりで突く訓練をさせられる女学生
祖母が女学生時代、竹やりで敵兵を突く訓練をさせられたそうです。当時の女学生でも相手が銃を持っていたら竹やりで叶うわけがないと思うそうで、「銃で撃たれたら突く前に死んでしまう」とおしゃべりしていると憲兵みたいな人にまじめに訓練しろと酷く怒られたと言っていたそうです。
祖母は8人兄弟で2人戦死しています。
1年程寝込んだ高祖母
ずっと女系だった家系で高祖母は男3人を生みました。やっと分家ができると喜んでいたものの、下2人の息子が学徒出陣で徴兵され戦死します。どこの石かもわからない石が戻ってきました。曽祖父がその人のためだけに作ったお墓には、石ころが入っておりニューギニアで戦死と彫られています。本当にニューギニアで亡くなったのかもわかりません。高祖母は約1年くらい寝込んで動けなかったそうです。
雇っていた若い男衆はみんな徴兵されてしまった
当時は手広く商売をしていて、若い男性を何人も雇っていたそうです。しかし太平洋戦争の末期、若い男性たちはみんな特攻隊員として徴兵されてしまい誰一人戻ってきませんでした。それから曽祖父は誰一人新たに雇うことはありませんでした。
特攻が決まったことを誰にも言うことはできません。だから、曽祖父宛に「お世話になりました。」というお手紙だけが届いたそうです。本当にお世話になったという感謝の言葉だけ。曽祖父はそれで察し、すぐにご両親に何も言わずただ一緒に会いに行こうと連れて行ったそうです。最後にご両親に会わせてあげていたそうです。
その後すぐに出撃したそうですが、最後に祖父の家の上空を低空で飛び数回旋回して旅立っていったそうです。音がするとすぐに家の外ででだそうです。白い絹を首に巻き、零銭に乗って出陣していく彼らはとても格好良かったそうです。祖父が「格好いいな」というと曽祖父は激しく怒ったそうです。
自分の家族も捕虜になり暴行をうけているのだろうか
墜落したのか不時着したのか敵兵を捕らえていたとき、集まった町民がみんなで蹴ったり殴ったりと暴行をしていたそうです。その中で見ていたある夫人が「出征している夫も捕まったらこのように暴行されるのだろうか」とつぶやいたそうです。それを聞いて暴力をふるっていた人もみんな止まったそうです。出征した自分の身内や知人などを重ねてみたのでしょう。
終戦記念日に毎年涙する曽祖父
毎年終戦記念日になると毎年涙を流していたそうです。
言葉にできない感情
間接的にそして断片的に聞いた話から、私は太平洋戦争中であっても戦争に行きたくて行ったわけではない、死にたいと思っていない、生きて帰りたい・帰ってきてほしいと誰もが思っていたと思います。
本気で「万歳」という人がいたのか、「日本のために死にたい」と思っていた人がいたのかと疑問に思います。多くの人が本音を言えない状況で、本当の気持ちを思いを飲み込んで、どうにもできないことに言葉にならない感情を持っていたのではないのかと。
あるドキュメンタリー番組で沖縄戦に従事された方の話では、戦争ドラマや映画では万歳をしながら亡くなっていく姿が描かれていることがあります。しかし、亡くなるときに万歳している人を見たことがない、「お母さん」と呼んで亡くなっていく方も多かったという話を聞きました。
万歳三唱は0ではなかったのかもしれませんが、おそらくそれだけではなかったのだと思います。1人1人にエピソードがあり、私たちがいまだに知らなかった何かがあるのかもしれません。
戦争について直接聞いたことのない私は分かりません。戦後、高度成長期も終わっただいぶあとに生まれた私には想像することも難しい。
学校の授業で「戦争について聞く」というものがありましたが、祖母も曾祖母もそれについて答えはなくズレた答えが返ってきました。その時は話がわからない人たちだと思いましたが、今思うと孫ひ孫に話したくなった・聞かせたくなかったから話を逸らしたのかなとも思いますが、真実はわかりません。